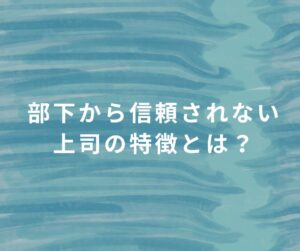マネジャーであれば、誰もが実施している業務支援。
同じ時間を使うなら、より効率的、効果的な業務支援にしたいですよね。
今回は、管理職に求められる3つの支援と、業務支援のポイントについて解説します。
マネジャーに求められる3つの「支援」
支援とは、「力を貸して助けること」です。
例えば、メンバーの仕事の判断にアドバイスする、進め方を指示をする、失敗した際にお詫びに同行する、こうしたことは業務支援です。
一方で、業務は進捗したとしても、メンバーの成長機会を奪ったり、自律性を損ないモチベーションを低下させたり、マイナス影響が大きくなってしまっては、効果的な支援とは言えません。
多くのマネジャーは「組織の目標達成」と「メンバー育成」の役割を担っています。
社は毎年成長し続けることを求められるため、組織の目標も年々高まる傾向があり、継続的に成果を出し続けるには、メンバーの成長が欠かせません。
マネジャーは、単に業務を支援するだけでなく、以下の3つの支援を意識的に行うことが必要になります。
- 業務支援 : 適切な仕事を任せ、相談やアドバイスをすることで、業務を進捗させる
- 精神支援 : 職場環境や人間関係を良好に保ち、内発的動機づけでやる気を引き出す
- 内省支援 : 客観的意見や新たな視点を与え、振り返る機会を作ることで成長を促す
業務支援は仕事を任せるタイミングから始まる
業務支援は、「何か問題が起きた時にサポートする」「発生ベースで対応を考える」といった問題が起きてから対処を考える方が多いですが、業務をアサインするタイミングが最も重要です。
例えば、「いついつまでにこれをお願い」と納期やタスクだけ示してアサインした場合、メンバーは目的や背景に関しては想像して仮説の中で進めるか、目的や背景を考えずに進めるでしょう。
少ない情報から間違った解釈で進めてしまう可能性も出てしまいますし、最初からやり直しということもあり得ます。
アサインタイミングで、いかに目的や背景を伝えきちんと仕事を任せるかによって、メンバーの仕事の進めやすさや、コミットメントは変わってきます。
仕事のアサインタイミングで必要なこと
仕事のアサインタイミングで意識すべきは、育成や動機づけの視点を持ち、自分と全く同じ進め方を期待しないことです。
- 業務遂行の視点だけでなく、育成の視点、動機づけの視点を持つ
- 自分と全く同じ進め方を期待しない(メンバーの工夫を受け入れる)
- アサイン時、目的や制約条件をしっかりと説明する
- 理由や期待を添えて仕事を任せる
- 中間報告を求め、そこまではメンバーに任せる
業務遂行の視点だけで考えると、1から10までやり方を指示する仕事の任せ方も効率的に見えます。
しかし、業務支援は少なく済むかもしれませんが、メンバーは自己決定感を感じることができず、ただ作業をこなすことになり、やりがいを感じることができなくなります。
アサイン時は、目的や制約条件をしっかりと説明することで、ゴールイメージをメンバーと共有しましょう。
ゴールイメージさえ目線合わせができていれば、メンバーは遠回りしてでも着実にゴールに近づくことができます。
また、アサイン時に納期を伝えるだけでなく、中間報告を依頼しましょう。
報告タイミングを設けておくことで、そこまではメンバーに任せることができるようになります。
メンバー側から報告や相談をするようになると主体性が生まれ、その場でフィードバックすることで成長機会にもなります。

業務支援でマネジャーに必要な意識と行動
メンバーの仕事ぶりを見ていると、どうしても判断の間違いや非効率な進め方に目が向きます。
そのこと自体は仕方ありませんが、良い業務支援のために重要なのは「どのように指摘すればメンバーの成長につながるか」です。
- メンバーの成長のためにフィードバックする
- タイムリーにフィードバックする(経験が新しいうちに)
- 承認と指摘のバランスを意識する(指摘だけにならないように)
- 具体的な改善点やその理由をフィードバックする
- 相談しやすい状況を作る(物理的、感情的に)
メンバーの気になる行動があった時は、放置せずにその場で一言声をかけましょう。
その人なりの理由があってその行動をとっているはずですが、数日後ではその時の感情やロジックを覚えていない可能性もあり、フィードバック効果が薄れます。
時間がない場合は、最悪メモやメッセージでも構いません。
タイムリーにフィードバックすることを意識してください。
業務支援の場面で多い過ちは、支援のつもりが指摘するだけになっているケースです。
メンバーが自分なりに考えて業務を進めている中で、マネジャーから指摘ばかりされたらどう感じるでしょうか?
認めてもらえず指摘ばかりされるのは、内容がいかに真っ当で正しくても、マイナスな感情をいだき成長に繋がりません。
「積極的に行動しているのはとてもいいね。」と行動を承認した上で、「もう少し〜〜を意識してみて」とアドバイスしたり、「どんな意図(目的)でその行動を選んだの?」と指摘したいポイントを内省させるなど、メンバーの感情的に受け止めやすいフィードバックを心がけましょう。
また、「それは違う」「成功するイメージがない」など否定だけで終えず、必ずその理由や具体的な改善ポイントをフィードバックするようにしましょう。
何が良くないのか原因がわからないものは、メンバーも改善のしようがありません。
メンバーから相談しやすい状況を作ることも重要です。
生産性を考えても、悩んだり迷っている時間が最も非効率です。
仕事を任せる時に中間報告を求めることで、納期まで悩み続けるリスクは無くせますが、中間報告までの期間悩んで過ごすのは時間がもったいないです。
「相談しづらい」と感じるのは、物理的理由と感情的理由があります。
マネジャーが忙しく物理的に相談する時間がないという場合は、先輩メンバーにメンターの役割を任せ、若手が相談しやすい状況を作るのがおすすめです。
感情的理由は、叱責を受けるのを危惧して相談しづらい、信用していないなどの信頼関係ができていない場合や、マネジャーが忙しそうで声をかけづらいなど配慮からくる相談しづらさもあります。
予め共有予定表などで「相談タイム」を設けてメンバーに分かるようにしておくと、メンバーはその時間に相談をくれるようになり、マネジャー自身もその他の時間は業務に集中しやすくなります。
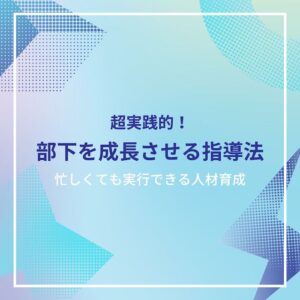
業務支援は、仕事のアサインから実際の業務支援までを一体として考えるとうまく行えるようになります。
- アサイン時に目的や制約条件をしっかりと説明し、中間報告を求める。
- 悩む時間を極力減らすために、相談しやすい状況を作る。
- 指摘だけで終えず、何が良くないのかその理由や具体的な改善ポイントを伝える。
これらのポイントを意識して、メンバーの成長につながる業務支援にトライしてみてください。