組織開発– category –
-
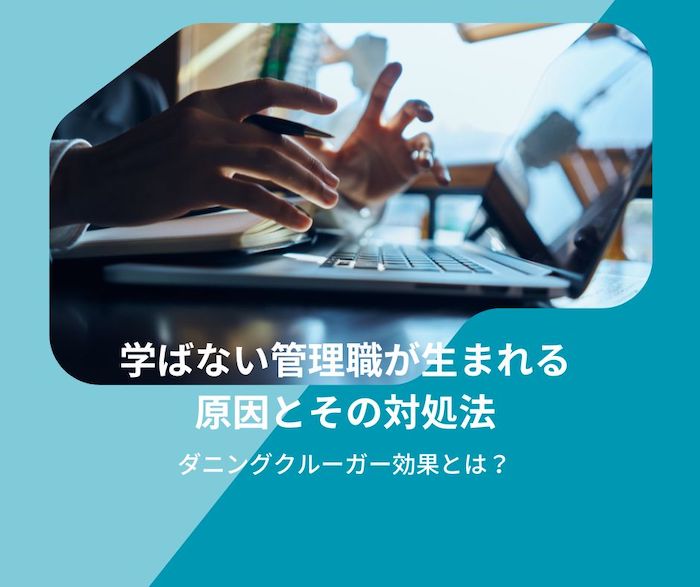
学ばない管理職が生まれる原因とその対処法|ダニングクルーガー効果とは
ダニングクルーガー効果とは、できない人ほど自分を過大評価するという認知バイアスです。今回はダニングクルーガー効果をもとに、学ばない管理職が生まれる仕組みとその解決方法について解説します。 -

なぜ人と組織は変われないのか?|変革を乗り越え目標を達成する方法
米ハーバード大学教授で発達心理学と教育学の権威である、ロバート・キーガンとリサ・ラスコウ・レイヒーによって書かれた『なぜ人と組織は変われないのか?』を参考に、人や組織が変われないメカニズムと、それを乗り越え変化する方法について解説します。 -

「反対意見を出すなら代案もセットで」は正しいのか?|反対意見がないのは良いチーム?
ミーティングや議論における進行ルールの一つに、「反対意見を出すなら代案もセットで」というものがあります。 今回は「反対意見を出すなら代案もセットで」という考えは正しいのか?と、前向きな反対意見を引き出す方法について解説します。 -
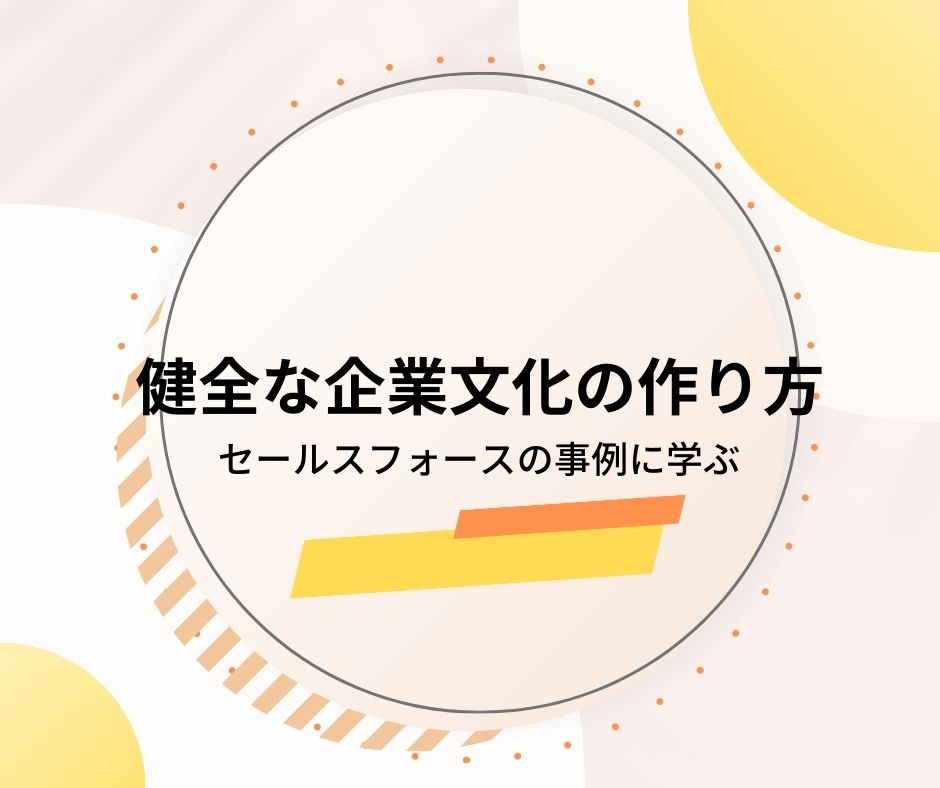
健全な企業文化のつくり方|セールスフォースの事例に学ぶ
今、企業文化が世界的に再注目されています。 今回は、CRM(顧客関係管理)プラットフォームの世界No1企業、「セールスフォース」を例にあげ、企業文化の重要性とその作り方について解説します。 -

適正なチーム人数とは?GAFAのセオリーと経営学から学ぶマネジメント
マネジャーのマネジメント人数はいったい何人が適正なのでしょうか?今回は、適正なチーム人数の目安と、マネジメント人数を増やす方法について解説します。 -
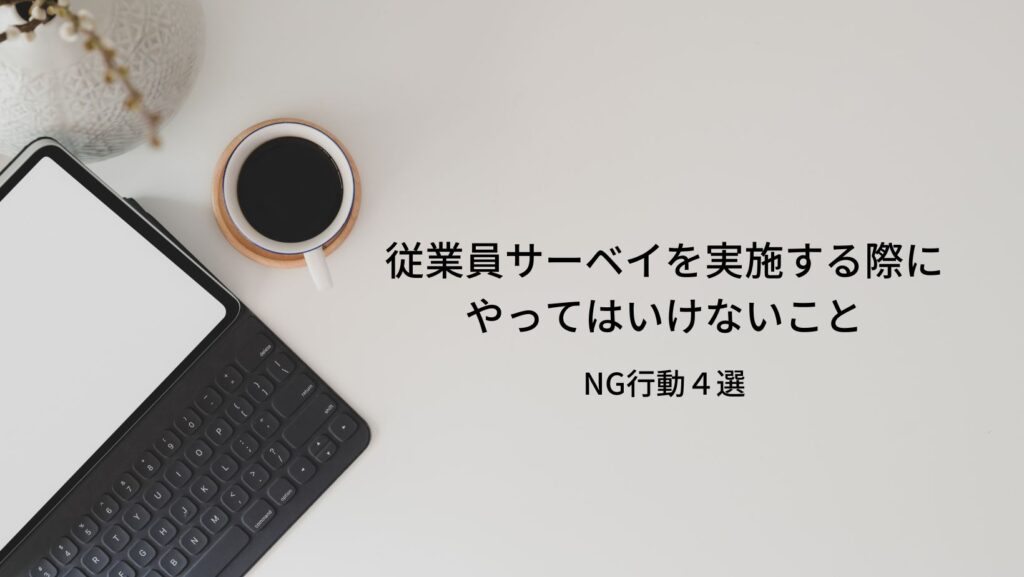
従業員サーベイを実施する際にやってはいけないこと|NG行動4選
サーベイは使い方を誤ると、組織にマイナスの影響を与えてしまうことがあります。 今回は、従業員サーベイを実施する際にやってはいけないNG行動を4つご紹介します。 -

リーダーになって感じる孤独|昇進うつ、管理職のうつにならないために
マネジャーや管理職になると誰もが感じる孤独。プレッシャーから、昇進うつ、管理職のうつになってしまう方も います。今回は、マネジメントの誰もが経験する孤独の原因と、その対処法について解説します。 -

【調査レポート】上司と部下の認知の差はどの程度か?
自己評価と他者からの評価の間には、誰しも多かれ少なかれギャップがあります。 従業員サーベイを実施すると、自己認知とのギャップに驚かれる管理職は少なくありません。 では、上司と部下との間には実際どの程度の認知の差があるのでしょうか? -

中間管理職に変化を起こす方法|マイケル・ウェイド氏に学ぶ組織論
会社の中で重要な役割を果たす「中間管理職」。今回は中間管理職の変革を作り出す方法について解説します。 -

変化に適応し、イノベーションを生む組織論|ダイナミック・ケイパビリティ理論
ダイナミック・ケイパビリティとは、経営学の世界で近年最も注目されている理論の一つです。同理論から、変化の激しい時代に企業はどのように適応し、イノベーションを起こせばよいのかについて解説します。 -

【調査レポート】マネジメント力は経験によって高まるのか?
ベテラン管理職と新任管理職の間には実際マネジメント力の差があるのでしょうか? 今回は、ベテラン管理職と新任管理職に分けて一風変わった調査を行いました。 -

両利きの経営とは?|新規事業を生み出す組織の作り方
スタンフォード大学教授のチャールズ・オライリー氏の著書『両利きの経営』から、新規事業を立ち上げる組織を作るためのヒントや、変化に適応する組織を作るにはどうしたら良いかを考えます。 -

上司と部下の間にある隔たりはどの程度か?
上司と部下との間にはどのくらい隔たりがあるのか?実際の管理職とその配下組織のデータで検証した結果をまとめています。 -

テレワークに対する管理職とメンバーの認識ギャップ|割れるテレワークの評価
各種アンケート調査では、管理職は「オフィスワーク(出社)」希望の声が多く、一般社員は「テレワーク(在宅)」希望が多いようです。今回は、管理職とメンバーで割れるテレワークの評価と、そのギャップの埋め方についてご紹介します。 -

マネジャーは組織に必要か?|Googleに学ぶピープルマネジメント
昨今、マネジメントを廃したフラットな組織運営をするスタートアップが登場したり、ティール組織、ホラクラシー組織、といった新しい組織体への注目が高まっています。これからの時代、マネジャーは組織に必要のない存在になってしまうのでしょうか? -

自分を振り返ることが難しい管理職|管理職の内省機会の作り方
従業員サーベイを実施すると、原因は思い当たらない、なぜだか分からない、と結果を受け止めることができず、内省が進まない管理職が一定数いらっしゃいます。 今回は、管理職の内省機会の作り方についてご紹介します。 -

従業員サーベイを活用するには?|より良い組織をつくるデータ活用法
近頃従業員サーベイを実施している企業が増えてきています。今回は、テレワークでのコミュニケーションを円滑にするために注意すべきことについて解説します。 -

マネジャーの姿勢が従業員エンゲージメントに与える影響|600組織を調査
「問題を解決しなければ、組織は良くならない」 私たちは、そのような漠然とした考えを持っているかと思います。 実際その考えが、解決が難しいと考えた場合、改善を諦めてしまう原因にもなっています。 しかし、どうやらその考えは事実と異なるようです。 -

メンバーシップ型(日本)とジョブ型(欧米)とは?|メリット・デメリット
最近ジョブ型雇用への注目が集まっています。今回はメンバーシップ型、ジョブ型それぞれのメリット・デメリット、運用の実態、ジョブ型導入による日本社会への影響について解説します。 -
|マネジャーの行動変容を妨げる心理的壁の乗り越え方.jpeg)
リーダーシップの経営心理学(後編)|マネジャーの行動変容を妨げる心理的壁の乗り越え方
マネジャーはなぜ知識はあっても実践できないのでしょうか?INSEADのナラヤン・パント教授の研究から、マネジャー育成の心理的な壁の乗り越え方について解説します。
12

